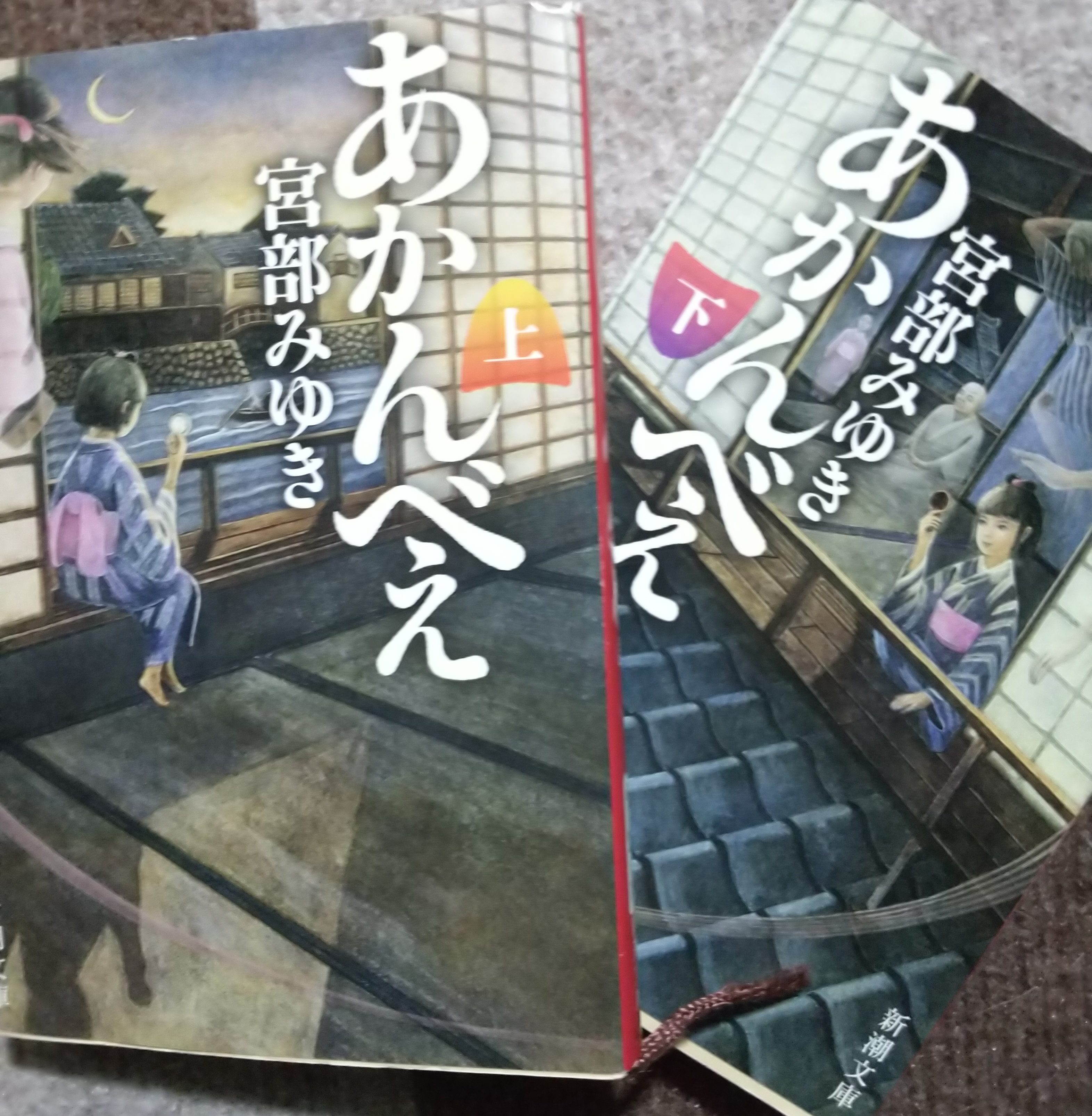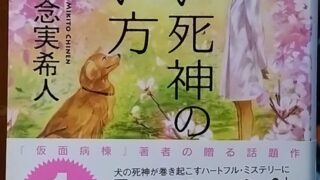新選組は、騒乱の京を守るため、そしておのれの志を貫き通そうとした侍たちでした。
身分を問わず集まった男たちが、なぜあれほどまでに強くなったのか。
ともすれば、烏合の衆に成り下がるかもしれない新選組を「鬼」の顔で守り続けたのは、副長の土方歳三だったといわれています。
今回は、土方歳三の生涯、新選組の絶頂期から仲間たちの別れまでをお話しします。

あらかじめお断りしておきますが、この記事は史実に基づきつつ、私個人の妄想や想像も加わっています。
どうぞご了承の上、お楽しみくださいね。
異分子来たる 伊東甲子太郎
「武士は江戸に限る」
近藤は、よく言っていたそうです。
そのため新選組は、たびたび江戸へ下り、隊士を募集しています。
元治元年は、池田屋事件・蛤御門の変と大きな戦闘が続いたこともあり、また新選組の仕事が一層増えたこともあり、この年の秋にも隊士募集のために江戸へ下りました。
今回の隊士募集は、まず試衛館からの仲間藤堂平助が江戸へ先行しています。
それは、藤堂の師匠に当たる人物に新選組への入隊を打診するためでした。
試衛館の分裂
新選組は、試衛館の仲間が主要なメンバーとしてここまで引っ張ってきました。
ですが、新選組の責任と規模が大きくなるにつれ、試衛館同士の中でも考え方が違ってきます。
その不協和音が次第に表面化してきました。
近藤が江戸へ隊士募集に行く直前の8月下旬には、永倉新八・斎藤一・原田左之助(ここまで試衛館以来のメンバー)・島田魁・尾崎雅次郎・葛山武八郎らの5人が、京都守護職松平容保に建白書を提出しています。
その建白書で永倉たちは、近藤の非行五ヶ条をあげ、
右五ヶ条について近藤が一ヶ条でももうしひらきあいいたさば、われわれ六名は切腹してあいはてる。もし近藤のもうしひらきあいいたさざるにおいては、すみやかにかれに切腹おおせつけられたく、肥後候(松平容保)にしかるべくおとりつぎありたい
『新撰組顛末記』より
「近藤が、永倉たちを同志としてではなく家来のように扱い、君主のようにふるまい、新選組を自分の好き勝手にしている」
「近藤が増長しているために、隊士たちがうんざりしてやる気をなくしている。このままだと新選組が瓦解してしまう恐れがある」
「これについて我々が納得するような申し開きを近藤がするなら、我々はすぐにでも切腹するが、申し開きができないなら、近藤に切腹をさせてほしい」
永倉たちはこのような内容のことを、新選組の雇い主である京都守護職に直訴したのです。
これには、松平容保も驚きました。
「新選組が解散などすれば、京都守護職が監督不行き届きといわれてしまう、ここはどうか穏便に…」
的なことを永倉たちに言ったそうです。
藩主にそういわれると、永倉たちもそれ以上無理は言えません。
容保は、早急に近藤を呼び出し、永倉たちと話合わせ酒を酌み交わして和解させました。
ですが、この火種はこの先ずっとくすぶり続けるのです。
永倉たちのこの行動を歳三はどう見ていたのか。
それが分かる資料はありませんが、ここからは私の想像ですが。
大きな組織となった新選組を規律厳しくまとめていくためには、仲間意識は邪魔になる。
近藤を中心として、副長からの命令を素早く、正しくいきわたらせるには、「なあなあ」の感情は捨てなくてはならない。
歳三はそう考えて、近藤にも隊士には区別なく威厳ある態度を示すようにさせたのではないでしょうか。
もうひとつ、剣の流派の違いも考えられます。
同じ試衛館に暮らしていても、近藤、沖田、井上と歳三は天然理心流。
永倉は神道無念流。
山南敬助、藤堂平助は北辰一刀流。
原田左之助は種田流槍術。
斎藤一は一刀流。
剣の流派が同じというのは、今の私たちには想像できないような深い絆があるといいます。
試衛館の仲間同士より、同門の仲間のほうが強いことも多いのです。
新選組の分裂を見るとき、流派に注目するのも興味深いですよ。
伊東甲子太郎の入隊
永倉の建白書には名前を連ねなかった藤堂ですが、彼も近藤や歳三のやり方には不満を持っていました。
このままでは新選組は幕府の用心棒に成り下がる。
新選組の初めの目的は尊王だったはずだが、その意思が近藤たちには見えない
もう一度原点に返って新選組をやり直すには、近藤・土方ではだめだ。
そう思った藤堂は、同じ北辰一刀流の師匠である伊東甲子太郎を頼みにしたのです。
永倉新八が残した言葉によると、藤堂は伊東にこのようなことを話したそうです。
「近藤は、今や幕府の走狗になっていり、当初の目標だった勤皇のことなどいつできるかわからない。新選組の現状に憤り、脱退するものも多い。
今回近藤が、江戸へ来るにあたり、彼を暗殺したうえで、あなた(伊東)に新選組を率いていただきたい。
そして、新選組を純粋の勤皇党に改めてほしいと思い、近藤に先立って江戸へ来た次第です」
試衛館で過ごした仲間がここまで言うほど憤慨していたことを、近藤も歳三も気づいていなかったのでしょうか。
生来の大将気質だった近藤はともかく、歳三は隊内の雰囲気や以前の仲間たちの心の内についてそれとなく感づいていたように思います。
でも、伊東の入隊による新選組瓦解の始まりまでは、想像していなかったかもしれません。
藤堂の申し入れに対し、伊東は驚きながらも、受け入れます。
ただし、近藤暗殺については同意しませんでした。
学識豊かで思慮深く、剣の腕も確かな伊東は、まず新選組の内情と近藤・土方という人間を見極めたうえで行動を起こそうと考えたのです。
歳三、最大のライバル現る
元治元年(1864年)9月
伊東甲子太郎は、実弟の鈴木三樹三郎、中西登、篠原泰之進、服部武雄らとともに上洛、新選組に入隊します。
歳三は、伊東の加入に際し、新選組の人事を改め、伊東一派を重職に抜擢しています。
伊東本人は、副長助勤、のちには局長近藤の次に位置する参謀に任命されました。
表向きは、伊東一派の入隊を歓迎しているという姿勢を見せたのです。
伊東一派、勢力を拡大する
伊東と同じ北辰一刀流の隊士は、藤堂のほかに山南敬助がいました。
実は、山南も試衛館時代に伊東と交流があったようで、藤堂と同じく伊東の入隊に大いなる期待をしていたと考えられます。
このころ山南は副長より上の地位である総長についていましたが、隊内での存在感はあまり大きくありませんでした。
伊東が入隊すると、その山南も頻繁に伊東と接するようになります。
ミスを犯したり、臆病な態度をとったことで歳三に厳しい処罰を下された隊士が、伊東の口利きで助かることもありました。
『新選組始末記』には「丈のすらりとした眼の涼しい美男」と書かれた伊東の隊内での人気は日に日に高まっていきました。
歳三が伊東についてどう感じていたのかは、わかりません。
ですが、今の新選組の姿は歳三にとって愉快なものではなかったはずです。
隊内は、近藤・土方派と伊東派に二分しつつありました。
山南敬助、脱走する
元治2年(1865年)2月
試衛館以来の仲間、山南敬助が脱走しました。
はっきりした原因はわかっていません。
ただ隊内では、歳三との確執が大きいのではと噂されていました。
大人数になってきた新選組に取り、壬生の屯所は手狭になってきていたため、歳三らは西本願寺への屯所移転を計画しました。
西本願寺は、長州を筆頭とする勤皇(このころは討幕派でもあります)の志士の味方をしているお寺でした。
そこで歳三は、あえて西本願寺に屯所を構えることで、にらみを利かせようとしたのだと考えられます。

西本願寺 京都フリー写真素材
山南は、この屯所移転に反対していました。
ですが、山南の意見など関係なく、歳三は強引に計画を進めます。
局長の近藤も歳三の強引な計画に文句を言いません。
穏やかで学識豊かな山南は、隊士の中にも慕われていましたが、山南本人は、新選組の中に自分の居場所はなくなったと感じていたのではないでしょうか。
でも私は、それだけで脱走するとは考えにくいと思います。
もしかしたら、伊東との何かしらの密約があり、江戸へ向かったのかもしれませんし、ほかに理由があるかもしれません。
北方健三さんの『黒龍の柩』では、思いもつかない歳三と山南の関係が描かれ、とても面白いです。
隊内での歳三と山南の確執は、実は…。
言いませんよ、読んでのお楽しみです!
元治2年(1865年)2月23日
大津の宿にいるところを追手の沖田総司に発見され、帰ってきた山南は、切腹しました。
介錯は、沖田総司。
山南の希望だったといわれています。
よく24日に山南の葬儀が行われました。
山南はその温厚な人柄で壬生村の人々にも慕われ、多くの参列者があったということです。
現在山南敬助は、壬生の屯所のほど近く、光縁寺で眠っています。
山南の切腹からほどなく、新選組は西本願寺へ屯所を移しました。
新選組 揺れる
元治2年4月初め
歳三は、新選組副長となって初めて江戸へ戻りました。
近づく長州征伐を見越した隊士募集のためです。
伴ったのは、伊東甲子太郎・斎藤一。
歳三が新選組を留守にする間、伊東が何をするかわからないとでも思ったのでしょうか。
歳三にとっては、虫の好かない伊東ですが、自分の近くに置いておくのが一番安全だと思ったのかもしれません。

ちなみに謎多き斎藤は、歳三がスパイにしていたという説もあります。
歳三、がっかりする
京へ帰ってきた歳三は、新選組の人事を改め、長州征伐を念頭に置いた「行軍録」を作成しています。
「行軍録」とは、戦における隊士全員の行軍体系を示した表のことです。
しかし結果的には、新選組は長州征伐の軍に加えられませんでした。
京における新選組の抜群の制圧力を維持したい幕府、京都守護職の意向があったともいわれています。
新選組にとって、池田屋以来の表舞台のチャンスがなくなり、歳三はさすがに落胆したようです。
しかし、長州が京へ攻め入る可能性も残っていたため、新選組は一層の鍛錬を怠りません。
歳三は、すでに剣のみの戦闘では勝ち目がないと悟っていたようで、西洋式砲術の訓練も始めています。
会津藩から大砲二門を拝借して、西本願寺の広い境内で毎日のように砲術訓練を行いました。
近藤、覚悟する
元治2年改め慶応元年(1865年)9月
幕府は長州征伐の勅許を得ると、長州への使節派遣を決めます。
長州に対し、幕府に従うつもりがあるか、反抗をやめるかなどを確かめるためでした。
すでに以前のような威勢もお金も無くなっていた幕府は、本当はあまり戦をしたくなかったとも考えられます。
近藤は、会津藩を通じて頼み込み、この派遣に随行し、これに伊東も従っています。
近藤は、池田屋以来宿敵となった長州を自分の眼でしっかりと確認したかったのです。
しかし、長州にとって新選組は、最大の仇です。
この時、近藤は歳三に「もし自分に何かあったら、新選組を頼む」と残しています。
故郷の多摩にも、「新選組のことは土方に託す、天然理心流宗家は沖田総司に譲る」という手紙を送っています。
近藤は、今回の長州行きに命を懸けるくらいの覚悟をしていたのです。
ところが、西国での新選組への警戒心はあまりにも強く、近藤は広島以西へ行くことは叶いませんでした。
慶応2年(1866年)になると近藤は再び広島入りしています。
この時も伊東が同行、ほかに尾形俊太郎、篠原泰之進が行きました。
伊東は、腹心の篠原とともに近藤とは別行動をとっています。
西国の勤皇の志士、討幕派と接触するのが目的だったようです。
いよいよ伊東が新選組の乗っ取りに動き出します。
伊東、動く
慶応3年(1867年)元日
伊東は、伊東一派のほかに永倉新八・斎藤一を誘って、島原の角屋で酒宴を開きました。
そして伊東は、永倉と斎藤を引き留め、4日の朝まで島原に居続けたのです。
普通なら、確実に切腹です。
これに激怒した近藤は、3人を謹慎処分にします。
伊東は近藤の部屋、斎藤は土方の部屋、永倉は別室で謹慎。
以前永倉が京都守護職に近藤の態度について直訴したことを近藤は、忘れていませんでした。
この時、近藤は永倉だけを切腹させようとしたのですが、歳三に止められ、3人の切腹は避けられました。
これは、伊東の近藤派切り崩し作戦だったのです。
しかし歳三のほうが一枚上手でした。
永倉には、近藤の永倉への処分を歳三が思いとどまらせたことで恩を着せ、伊東派に寝返ることをさせません。
歳三の部屋に謹慎している斎藤は、伊東の行動を逐一歳三に報告していたのです。
同年 3月
伊東甲子太郎は、とうとう新選組と別行動をとります。
伊東に従った中には、藤堂平助と斎藤一の姿もありました。
表向きは、新選組から分かれ御陵衛士という形をとることで、様々な情報を新選組に伝えるためとなっています。

高台寺月真院 御陵衛士の屯所になっていた 京都フリー写真素材
御陵衛士…孝明天皇の陵墓を守るための組織。高台寺月真院に屯所を置いたため、高台寺党ともいわれる
しかし、歳三にとっては、切腹という処分が待つただの脱退。
この先には、凄惨な粛清が待っているだけでした。
徳川幕府の終わり
松本良順は幕府御典医で、後々まで新選組の味方でいてくれた心強い人物です。
歳三、動く!
新選組の屯所が西本願寺に移ってからのこと。
ある日、松本良順が西本願寺の屯所にやってきます。
松本が屯所を見たいといったので、近藤は、歳三に案内させます。
大きな部屋には、170~180人ほどの隊士がいます。
刀の手入れをしている者、武具の点検をしている者やただ寝っ転がっている者もいます。
松本は、
「局長と副長が見回っているのに、寝ころんだままというのはあまりにも失礼な態度ではないか。規律が緩んでいるのではないか」
と指摘しました。
近藤は、
「あれはみな病人です。そのため、ゆっくり寝かしているのです」
と返答します。
実はこの時の新選組隊士は、その約1/3が何かしらの病気になっていて、その事実を知らされた松本は、非常に驚きました。
そこで、松本は、
屯所に別に病室を作り、病人をそこへ収容すること
医師の巡回と薬の投与をすること
看護係を置くこと
浴場を設置して清潔を保つこと
などを勧め、実際に西洋の病院の図を書いて近藤と歳三に見せました。
すると、不意に歳三がどこか行ってしまいます。
松本は近藤とともに、屯所を見て回ります。
2,3時間ほどたったころ、歳三がやってきて、
「先生に教えられたとおりに病室を作ってみましたので、見ていただけませんか」
と言うではありませんか。
松本が見に行くと、言ったとおりの病室が作られすでに病人が収容されていました。
浴場は3つも設けられていて、すっかり驚いた松本に、歳三は
「兵は拙速を貴ぶとはこのことですよ」
と大笑いをしたということです。
歳三の行動力の速さと、迅速に対応する部下との連携がとれていること、その手際の良さがよくわかる逸話です。
歳三、幕臣になる
慶応3年(1867年)6月
新選組は、幕臣になりました。
石高はわずかとはいえ、多摩の農民の子が幕府直参になったのです。
6月半ばに不動堂村に移した屯所は、まるで大名屋敷のような立派なものでした。
歳三は、自分が作った新選組の成長ぶりをどう見ていたのでしょうか。
この時、幕府はすでに息も絶え絶えの状態でした。
さかのぼること1ヶ月、5月には坂本龍馬の仲介による薩長同盟の密約が成立し、薩長は少しずつ討幕の準備を始めていました。
幕府の命はあとわずかだということを歳三はまだ知りません。
歳三、別れる
同年 9月末
歳三は、隊士募集のため再び江戸へ下り、日野の佐藤彦五郎家にも訪れています。
この時歳三は、許嫁だったお琴に別れを告げています。
お琴は、今から10年以上も前、歳三が19歳の時に兄の為次郎に紹介され、家同士により婚約した相手です。
しかし、歳三の
「自分には果たしたい大きな夢がある。だから結婚する気はない」
という一言で、婚約は破棄されたはずですが、お琴はずっと待ち続けていました。
もしかしたら、いずれ江戸へ帰ってきたら夫婦になるとの約束をしていたのかもしれません。
ですが、新選組副長として突っ走り、おそらくこれからも走り続けるだろう自分とはきっぱりと別れるほうがお琴のためだと思ったのでしょう。
でも女性目線から言わせていただくと、
「歳三さん、遅すぎます!」
お琴さんの年齢は、はっきりわかりませんが、この時代の適齢期は確実に過ぎています。
これからほかに嫁入り先を探すなんて、至難の業です。
お琴さんはそんなこと言わないだろうし、代わりに私が言います。
「どうせ別れるならもっと早くいってほしかったなあ」
徳川幕府の消滅
同年 10月14日
15代将軍徳川慶喜が大政奉還を申し出ます。
これにより、260年余り続いた徳川幕府は終わりを告げました。
歳三が、京を不在にしている間のことでした。
徳川幕府がなくなったことを歳三はどうも思ったのでしょうか。
それを知る手掛かりはありませんが、これ以後も変わりなく隊務に当たる歳三の姿は、また別のゆるぎない信念があったのかもしれません。
大政奉還を知った時の歳三を描いている小説はもちろん多いですが、私は木原としえさんのマンガ『天まであがれ』の歳三が好きです。(ただいま脱線中)
顔色一つ変えずにいつものように不機嫌な表情の歳三、それを見ている沖田の言葉。
「好きだなあ、僕は土方さんが。なにがあってもやっぱりいつも」
少女漫画なので、格好いいこと、この上ないです。
歳三、斬る
大政奉還後、世の中の動きはどんどん早くなっていきます。
11月15日
薩長同盟・大政奉還の影の立役者、今や最も人気のある幕末の志士、坂本龍馬が近江屋で暗殺されます。
これより5日前の10日。
斎藤一が月真院の御陵衛士屯所を抜け、歳三に伊東たちの近藤暗殺計画を知らせます。
歳三は、先手を打って伊東を暗殺する計画を立てました。
11月18日
歳三はかねてより、伊東から情報収集のための資金調達を依頼されていた件を利用し、伊東を
近藤の妾宅に呼び出しました。
御陵衛士の中には、これは近藤の罠ではないかと警戒し、伊東に誘いに乗らないように言う者がいましたが、生来自信家で楽天的な伊東は、それを無視します。
せめて誰か警護のものをつけるようにという助言も受けませんでした。
近藤の妾宅には、土方も同席し、伊東の論に笑顔さえ浮かべながら聞き入ります。
伊東は、機嫌よく飲み過ごし、すっかり酔っぱらってしまいます。
夜の8時を過ぎたころ、伊東は上機嫌で帰路につきました。
そして、木津屋町通りを東へ、油小路にかかったあたりで、待ち伏せした新選組隊士に襲われ、絶命しました。
油小路事件
伊東の遺骸は、油小路にそのまま放置されました。
伊東殺害を知らされた御陵衛士は、現場へ急行することになります。
待ち伏せしている新選組隊士は20名あまり、御陵衛士は、7名ほど。
藤堂平助が伊東の遺体を、籠に乗せようとしたのが合図のように、新選組が襲い掛かります。
少数ながら、御陵衛士は奮戦し、新選組側にも負傷者が出ますが、多勢に無勢。
次第に倒れていく御陵衛士たち。
新選組の側には、永倉新八もいました。
永倉は、襲撃の前に近藤から、藤堂平助は何とか助けるようにと言われていました。
全身を斬られながら奮闘を続ける前に永倉が出ます。
斬りあいをしながら、永倉はあえてスキを作り、藤堂を逃がそうとしました。
藤堂は、その情けを受け、永倉の横を通り過ぎようとした…と、その背中を別の隊士が斬りつけました。
三浦常太郎というその隊士は、藤堂に可愛がられていた隊士でした。
永倉が斬られると勘違いし、思わず斬ってしまったとはいえ、恩義ある藤堂の命を絶ってしまったことにひどく苦しんでしまいました。
藤堂は、歳三にとって沖田同様弟のような存在だった。
この事件は歳三の中でも苦い思い出となっていたことでしょう。
新選組 京を離れる
慶応3年12月9日
王政復古の大号令が出されます。
朝廷による新政府が立ち上げられ、京の都は討幕派が支配するようになります。
12月16日
新選組は、旧幕府軍と薩長を中心とする討幕派との戦に備え、不動堂村の屯所を引き払い、伏見奉行所に布陣します。
この後新選組は二度と京に戻ることはありませんでした。
12月18日
近藤は、二条城での軍議の帰り道、伏見街道の墨染あたりで狙撃されました。
近藤を襲ったのは、御陵衛士の残党です。
右肩に重傷を負った近藤は、かろうじて落馬せずに伏見奉行所まで戻ってきました。
気丈にふるまう近藤ですが、傷は思った以上に深く、伏見では手当もままならないために、松本良順のいる大坂城へ移されることになりました。
歳三は、近藤とともに沖田も大坂へ移します。
この時はすでに労咳(結核)の病状が進み、刀を持つこともままならない状態だった沖田ですが、
「近藤さんは私がお守りしますから」
と明るく言って歳三を困らせずに発ちました(注:妄想!)
これ以後新選組は、歳三が指揮します。
近藤という大将がいなくなった今、歳三は将としていかに戦うのか、そしてその最期は。
土方歳三の生涯、思いのほか長~い記事になっていますが、おそらく多分もしかしたら、次が最終回の予定です。(予定!)
今回も最後までお読みくださりありがとうございます。
ではまた次回!
土方歳三ゆかりの場所
今回登場した歳三ゆかりの場所はこちらです。