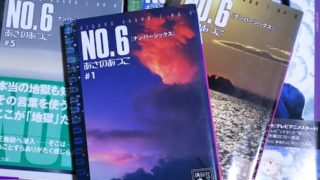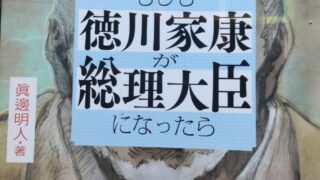幕末騒乱の京の都。
攘夷志士たちによる暗殺事件が頻発していた中で、京の町を警護しようと働いた新選組。
たった5年の活動期間だったにもかかわらず、今の私たちに鮮烈な印象を与えています。
今回は、土方歳三が新選組を作り上げ、幕末最強の武士集団に育てていくまでに注目したいと思います。
土方歳三は、個人的に思い入れが強すぎるため、時に妄想が入ったり、暴走したりすると思いますので、予めご了承くださいね。
土方と新選組の生きざまをどうぞご堪能ください。
浪士組から壬生浪士組へ
清川八郎率いる浪士組に参加して京へやってきた歳三ら試衛館一行でしたが、清川の策が幕府に知られ、浪士組は再び江戸へ帰ることになりました。
将軍警護のお役を果たそうと、道場をたたんで京に来た近藤は、江戸へ帰ることを拒否。
試衛館の面々は京へ残ることになります。
同じ宿舎に泊まっていた水戸脱藩浪士芹沢鴨一派も京残留組となります。
さてここから、いかにして今日で活動すべきなのか。
何のつてもない近藤たちはいったいどうするつもりなのでしょうか。
会津藩お預りになる!
京に残った歳三たちは、浪士組宿舎として泊まっていた壬生の八木邸にそのまま居候を決め込みます。

八木邸の人たちはさぞ迷惑だったと思います。でもよくぞ彼らを受け入れてくれました
近藤の「将軍の警護及び京の町を守る」という愚直なまでの初心を貫くべく、八木邸の居候たちは、自主的な京の見回り警護を始めます。
と同時に、京都守護職会津藩藩主松平容保に嘆願書を提出しました。
将軍が京を離れるまで市中見回りの許可を求める嘆願書でした。
そして…。
文久3年(1863年)3月15日
京都残留組は、黒谷にある会津本陣へ招請され、藩主松平容保に拝謁することになりました。
この時の近藤、歳三らの胸中はいったいどんなものだったのでしょうか。
農民という身分にありながら、武士になりたいとあこがれ、将軍の警護をするために京へ上った彼らでしたが、まさか会津藩主に拝謁できるなんて考えもしなかったと思います。
その感激、驚きは、私たちには到底想像できないほど大きなものだったと思います。
松平容保は、近藤、歳三たちに言葉をかけます。
「これからは、わが会津藩士らとともに助け合って京を守ってほしい。頼んだぞ」
多摩の田舎から出てきた歳三たちにとって、会津藩主直々の言葉はどれほどの感激をもたらしたことでしょう。
彼らが最期まで会津藩とともに戦う道は、この瞬間決まったのです。
浪士組を抜けて、京に残った者は、八木邸の面々以外にも殿内義雄・家里次郎・佐伯友山・粕谷新五郎・阿比留鋭三郎など数人おり、計24名が松平容保と拝謁したとされています。
しかしこの後1か月ほどの間に、派閥争いにより暗殺されたり、逐電したため、八木邸のメンバーが主導権をとるようになりました。
かくて「会津お預り 壬生浪士組」の誕生です!
壬生浪士組 活動開始
文久3年4月11日
壬生浪士組は、攘夷祈願をするために石清水八幡宮へ行幸する孝明天皇の道中警護をします。
壬生浪士組として初めての警護。
みんな張り切ったでしょうね。
同年4月16日
会津本陣にて松平容保に武術披露。
初仕事ののわずか5日後、松平容保から謁見を望まれます。
謁見の場で会津藩主は突然、「そなたたちの武術稽古をみたい」と命じます。
歳三たちはさぞ驚き、興奮したことでしょう。
歳三はなんとトップバッターです。
対する相手は、藤堂平助。
秋山香乃さんの小説『歳三 往きてまた』では冒頭にこの場面が出てきます。
少し長いですが、歳三と藤堂の立ち姿がとても素敵に描かれていますので紹介します。
会津側からため息が漏れた。どちらも容姿が傑出していたからだ。艶やかで豊かな黒髪に白い肌の対比なら、主君容保の貴族的で優美な姿を見慣れていてもいたが、土方には加えて野性味を帯びた獣のようなしなやかさがあった。一方の藤堂は、物静かな顔立ちに澄んだ瞳が爽やかな印象を残す青年だ。 『歳三 往きてまた』より
ちなみに2番以降は、以下のようなメンバーでした。
- 永倉新八vs斎藤一
- 平山五郎vs佐伯又三郎
- 山南敬助vs沖田総司
- 川島勝司(棒術)
- 佐々木愛次郎 佐々木内蔵之丞(柔術)
歳三、組織作りをする
身分を問わず、腕の確かなものなら入隊できるといううわさが広がり、壬生浪士組に入隊する隊士はどんどん増えていきます。
歳三は、壬生浪士組が烏合の衆にならないためにもしっかりした組織体系が必要だと考えます。
多摩にいたころ、秘伝の石田散薬を作るための薬草を取るとき、多くの人を使って効率よく仕事をするすべを知っていた歳三は、組織とその命令系統がいかに大事かを知っていました。
近藤や物知りの山南らと検討を重ね、作り上げた組織の主な役職がこちら。
局長:芹沢鴨 新見錦 近藤勇
副長:山南敬助 土方歳三
副長助勤:沖田総司 永倉新八 原田左之助 藤堂平助 井上源三郎 平山五郎 野口健司 平間重助 斎藤一 尾形俊太郎 山崎丞(すすむ) 谷三十郎 松原忠司 安藤早太郎
調役:島田魁 川島勝司 林信太郎
勘定方:岸島芳太郎 尾関弥四郎 河合耆三郎 酒井兵庫
(太字が試衛館からのメンバーです)
命令系統は局長から副長へ、副長から助勤以下へ下ります。
つまり、直接命令するのは副長の山南と歳三ということです。
歳三は、実戦に対する部隊を直接指揮するという最適のポストを確保したのです。
隊を引き締める最強のルール局中法度
新選組を語るうえで有名なのは、厳しい罰を定めた局中法度です。
永倉新八が残した『新撰組顛末記』では、「禁令」として以下のように定められたと記されています。
第一 士道に背くこと
第二 局を脱すること
第三 勝手に金策をいたすこと
第四 勝手に訴訟をとりあつかうこと
この四箇条をそむくときは切腹をもうしつくること、またこの宣告は同志の面前でもうしわたすこと
(局中法度という言葉は、実は子母澤寛さんが『新選組始末記』の中で、この条文を整理して編集したものです)
『新撰組顛末記』では、この禁令は芹沢、近藤、新見が定めたと記されていますが、直接宣告するのは副長の歳三が山南になるので、おそらくこの二人もかかわっていたはずです。
この法度が定められたことで、壬生浪士組の隊士たちは身が引き締まる思いになったでしょう。
壬生浪士組から新選組へ
壬生浪士組は、市中見回り・不定浪士の取り締まりなど日々の警護を続けましたが、世情はどんどん不穏になりつつありました。
文久3年8月18日
禁門の政変(八・一八の政変)が起こり、壬生浪士組は会津藩の下知により御所へ出動。
この働きにより、「新選組」の名を拝命します。
ここに「新選組」の名が初めて歴史上に登場しました。
同年8月22日
京都守護職から福岡藩脱藩浪士平野国臣の捕縛を命じられます。
歳三が指揮した捕縛班は、三条縄手方面を捜索、24日には旅宿豊後屋へ踏み込みます。
歳三は、この出動を”三条縄手の戦い”と称して、日記にしたためていたらしいです。
歳三にとってもハレの舞台だったのでしょう。
のちに禁門の政変でも使用した鉢金とともに佐藤彦五郎に送っています。
現在日記は所在不明ということですが、鉢金は土方歳三資料館で見ることができます。
歳三、邪魔者を消す
歳三たちとともに京に残った芹沢鴨一派(新見錦・平山五郎・平間重助・野口健司)は、日に日に横暴な態度をとるようになっていました。
大坂出張の折には、芹沢の行く手を(ふざけて)ふさいだ相撲力士を斬り捨てたり、島原の角屋で暴れまわったり、大坂新町の芸奴の髪を切ったり、挙句の果てに大和屋という商家の蔵に大砲を打ち込んだり。
近藤たちがまじめに市中見回りをしても、目立つのは芹沢たちの悪評ばかり。
新選組は「壬生狼」と呼ばれて、京の人々から恐れ、嫌われていました。
近藤を担ぎ上げ、新選組を大きくしようと考える歳三にとって、そんな芹沢たちは邪魔者でしかありません。
折しも会津藩からそれとなく芹沢の処分を命じられます。
しかし…。
「芹沢は、神道無念流の凄腕。まともに斬りあっても太刀打ちできるのはおそらく総司、それも相打ち覚悟の斬りあいになるだろう」
そう考えた土方は、だまし討ちを決意します。
だまし討ちを決意した段階で、近藤には直接手を下させないと決めます。
「近藤さんには手を汚させない。それは俺の役目だ」
歳三は、まず腹心の新見錦を法度違反で切腹させます。
新見錦を失った芹沢は、一層荒れます。
文久3年9月16日
禁門の政変の功績に対し、会津藩から報奨が出たということで、この日は島原で大宴会が行われます。
芹沢は相変わらず大酒を飲みご機嫌です。
歳三も今日はいやに愛想がよくて気持ち悪い…。
芹沢・平間・平山は屯所になっている八木邸に帰ると、待っていた相方の女性と再び宴会をはじめ、いつの間にか寝入ってしまいました。
外は土砂降りの雨です。
真っ暗な雨の中を歳三、沖田、原田、山南が静かに芹沢たちの寝室に近づきます。
翌日芹沢と妾のお梅、平山が惨殺された姿で見つかりました。
(平間とその相手の糸里、平山の相手吉栄は逃げ出しています)
芹沢らは急死として届けられ、隊内では長州の刺客に斬られたということにされました。
2日後、近藤は芹沢と平間のために立派な葬儀をあげました。
新選組の主要メンバーは、大半を近藤派になり、歳三の新選組が始まります。
同時に歳三は血の粛清をすべて引き受ける覚悟をするのです。
平間重助とともに逃げたといわれる糸里を主人公にした浅田次郎さんの『輪違屋糸里』は、糸里から見た歳三や芹沢、平間を描いています。
女のしたたかさや隊士たちの弱さが垣間見えて、新選組をテーマにしたものの中では趣の違った面白い作品です。
あまりにも短い新選組の絶頂期
元治元年(1864年)は、徳川家茂の再入洛の警護から始まりました。
そして、新選組を一躍有名にしたあの事件が起こります。
池田屋事件、そのはじまり
この年の4月ごろから多数の長州藩士ら反幕派が、京で潜伏していることが分かって以来、探索活動を強化していた新選組。
5月に入ると四条小橋上ル「枡屋」という炭薪商が怪しいとわかってきました。

古高俊太郎邸跡写真提供:京都無料画像
歳三らは、会津藩に連絡をしたうえで更に探索を続けます。
元治元年6月5日 早朝
枡屋を急襲、家宅捜索をし、土蔵から多数の武器弾薬、会津藩のニセ提灯、手紙などが見つかります。
捕縛した当主の湯浅嘉右衛門は、本名を古高俊太郎。
長州と気脈を通じる反幕派の男でした。
屯所へ連行された古高の取り調べが始まります。
始めは局長の近藤が、みずから取り調べますが、死を覚悟した古高は口を割りません。
そこで歳三が近藤に代わり、古高を調べます。
背中の皮膚が破れるほど、打たれても何も話しません。
反幕派には、古高が捕縛されたことはすでに知られているはず、いきり立った反幕派が今にも屯所へ斬りこんでくるかもしれないという切迫した状態で、歳三は最後の手段ともいうべき拷問を実行しました。
古高を土蔵の梁に逆さづりにすると、足の裏に五寸釘を打ち込み、それへ百目ろうそくを立てて、火をつける…熱い蝋が流れて足裏の傷口へ流れてゆきます。
この残忍な責めに、古高は小半時(約30分)ほどもだえ苦しんだ後、ようやく口を開きます。
その過激な内容に歳三たち新選組は驚愕します。
とんでもないクーデターでした。
池田屋事件 突入
近藤は、この陰謀をすぐに会津藩へ報告し、即座に隊士を招集、大規模な京都市中探索の準備を始めます。
6月5日 午後8時ごろ
新撰組は、祇園石段下の祇園会所へ集合、会津からの命令を待ちますが、約束の刻限(8時)を過ぎても何の連絡もありません。
じりじりと待っていた近藤、歳三たちですが、これ以上遅くなれば浪士たちの捕縛が不可能になるかもしれないと考え、単独で行動することを決心しました。
浪士たちが集まるのは、反幕派が多数出入りしていた旅籠池田屋と四国屋の可能性が濃厚だと考えられたが、探索をその2軒に絞るのはあまりにも無謀です。
折あしく、病人が多数出ていた新選組は、動員できる隊士が不足していました。
近藤と歳三は、わずかな人数を3隊に分けます。
近藤隊 沖田総司 永倉新八 藤堂平助 原田左之助ほか(計9名とも10名ともいわれています)
土方隊 斎藤一 島田魁ほか(約13名)
井上源三郎隊 約13名
隊編成の人数割りには諸説あります
談合は池田屋で行われていました。
池田屋の探索に入ったのは、近藤隊。
中にいる浪士は約30名。
近藤たちは、決死の覚悟で屋内へ。
永倉新八が残した『新撰組顛末記』ではその時の様子が、詳しく描かれています。
斬りあった永倉本人が言ったことですから、リアルです。
命がけの斬りあいが続く文面には迫力があります。
斬りあいの途中、藤堂が額を斬られ、沖田はもうろうと倒れます。
永倉も左親指の付け根を斬られてしまいますが、近藤の甲高い気合は聞こえます。
池田屋が本命だったと連絡を受けた土方は、急ぎ池田屋へ駆けつけます。
この時の歳三の行動がどのようなものだったのかはわかりません。
ですが、司馬遼太郎先生の『燃えよ剣』ではこのように描かれています。
私はこの歳三のやり方がとても好きで今でも印象に強く残っています。
副長としては階下をまもって近藤にできるだけ働きやすくさせ、この討入りで近藤の武名をいよいよ上げさせようとした。(中略)
歳三の役目は、ほかにもあった。戦闘がほぼ片づきはじめたころ、会津、桑名の連中がともすれば屋内に入ろうとする。
いわば、敵が崩れたあとの戦場かせぎで、卑怯この上もない。
「なんぞ、御用ですかな」
(中略)新選組の実力で買いきったこの戦場に、どういう他人もいれないつもりである。
「おひきとりください」
底光りのするこの男の眼をみては、たれもそれ以上踏みこもうとしなかった。
『燃えよ剣』より
私は、歳三の近藤への熱い思いと信頼を感じるかっこいい場面だと思っています。
2時間にも及んだ池田屋の戦闘により、新選組の名は京をはじめ浪士たちの間にも広く知れ渡ることとなりました。
歳三、浮かれる
歳三は、そのイケメンぶりで京でもモテモテ。
池田屋事件で新選組の名が広まると、モテっぷりに拍車がかかりました。
隊内では、冷静沈着で通っている歳三でしたが、郷里には愛嬌いっぱいの手紙を送っています。
文久3年の秋には、新撰組の運営がうまくいっているという仕事の話の後、自分がどれだけモテているかを書き綴っているのです。
いわく、「京都島原の花君太夫・天神・一元。祇園の芸子三名、北野の舞子の君菊・子楽、大坂新町の若鶴大夫のほか二、三名、北の新地では多すぎて書ききれないほどだ…」
ついでにこんな俳句とツッコミまで
「報国の心をわするる婦人かな」 歳三いかがわしきよみ違い
池田屋事件の後、元治元年9月には、土方の遠縁にあたり新選組の支援をしていた多摩の小島鹿之助へ女性たちからもらった恋文まで送っています。
歳三の浮かれた、ちょっと子供っぽい表情にほっとしますね。
これらのお話は、小島鹿之助資料館の館長が書かれた『幕末群像伝 土方歳三』に書かれています。
歳三や近藤と親交のあった小島家に残る資料などから見た歳三の素顔を知ることができますよ。
歳三、慟哭する
池田屋事件以後、反幕派・討幕派の浪士たちの残党狩りが続いていました。
新撰組には、会津藩より応援として柴司以下数名の藩士が派遣され、引き続き市中取り締まりと、市中探索を強化していました。
そんな中、東山の料亭明保野亭に不審な浪士の影を見つけ、追いかけます。

三年坂 この途中に明保野亭がある 京都フリー写真素材
新選組隊士とともにいた柴司は、その中の一人を槍で突くと、相手は土佐藩の麻田時四郎と名乗ります。
当時土佐藩は会津藩とは友好関係にあったため、柴は非礼を詫びて麻田を放します。
しかしこれが土佐藩、会津藩に知れたことで大きく事態が動きます。
土佐藩は、見舞いもかねて会津藩がよこした医者を丁重に拒絶。
その口ぶりから、「士道不本意」という理由で麻田が切腹すると知ります。
明保野亭での一件を柴司から報告されていた会津藩主松平容保は、
「本人には落ち度はないが、会津藩と土佐藩の友好関係を崩さないためには柴に切腹をさせなければならない、だが自分からはそんなことは言えない」
と涙を流したといわれています。
すべてを悟り受け入れた柴司は、潔く切腹をします。
享年21歳。
会津藩と土佐藩の関係は保たれ、両藩は柴司の死に敬意を表しました。
柴の葬儀には、歳三、井上源三郎、武田観柳斎、河合 耆三郎、浅野藤太郎の5名が参列し、歳三らは、柴の死を悼み、遺体にすがりついて悲しんだと伝わっています。
柴の遺体は、黒谷金戒光明寺の会津藩士の墓地に埋葬されましたが、歳三たちは涙を流しながらこれに同行したのです。

金戒光明寺にある会津藩士墓地 京都フリー写真素材
歳三の覚悟
柴司の死は、武士になることを夢見ていた歳三に、大きな衝撃を与えました。
「士道不覚後」の死。
士道とはどういうものなのか、歳三の中で「士道」に対する強烈な憧れと畏怖をはっきりと感じる事件になったのではないでしょうか。
柴司の切腹は、歳三を「鬼」に変貌させるきっかけとなるのでした。
蛤御門の変 勃発
池田屋事件で大打撃を負った反幕派は、会津藩と新選組、薩摩藩への怒り恨みを深めてゆきます。

薩摩藩はのちに坂本龍馬の仲介で薩長同盟を結びますが、このころは、幕府側についていました
反幕派の中心であった長州藩の過激派は、池田屋事件の一報を受けると激怒して京へ向かって進軍を始めます。
この動きは、会津藩にも伝わり、新選組も長州軍の京入りを警戒して師団街道を警護するために九条河原へ出陣しています。
しかし、幕府方の動きは鈍く、いつまでたっても出撃命令は出ません。
歳三たち新選組は、長州が嵐山の天龍寺に陣取っているらしいこと、長州が伏見の藩屋敷に布陣していることがわかっていましたが、上からの命令なしに動けないことにイライラしていました。
一方長州側も、穏やかに話し合いをすべく何度も朝廷に嘆願をしますが、受け付けられずにじりじりしていました。
元治元年7月18日
長州藩は、会津藩討伐という名目のもと、ついに京の市中へ進軍します。
新撰組は、伏見の長州屋敷への攻撃を準備している途中に伏見方面での砲撃の音を聞きます。
幕府側の大垣藩からの要請により、会津藩と新選組は伏見へ向かい、長州軍との戦闘に臨み、新選組は、長州軍を伏見稲荷から墨染あたりまで追撃します。
嵐山から進軍してきた長州軍の本隊は、御所の南側・蛤御門周辺で会津藩や薩摩藩と激戦を繰り広げました。
最も戦が激しくなった門の名前を取って、この戦が「蛤御門の変」と呼ばれています。
御所の激戦は伏見にいた新選組にも伝わり、歳三たちは急ぎ御所へ向かいましたが、主な戦闘はすでに終わっていました。
同年7月21日
蛤御門の変の残党狩りの命令が下り、新選組は天王山に向かっていました。
天王山に立てこもっていたのは、久留米の神官真木和泉守らわずか17名。
会津藩士とともに追撃をする新選組と真木らは、しばらくの銃撃戦の後、陣小屋に火を放ち、自害して果てました。
真木らの見事な最期に歳三ら新選組隊士、会津藩士らは感嘆の声を上げたといわれています。
近藤は涙を流していたともいわれ、武士の潔い最期は再び歳三や近藤の胸に刻み込まれたことでしょう。
少しずつずれていく新選組
近藤を担ぎ上げて土方が命令する。
この体制が新選組を揺るぎのない強い組織にしてゆきます。
ですが、試衛館の仲間の中には、次第に違和感のようなものを感じるようになる者が出てきます。
山南敬助、藤堂平助、永倉新八…。
彼らとの確執が表立ってきます。
歳三の新選組は、新しい入隊者により、思いもよらぬ方向へ動きます。
新選組は歳三も気づかないまま、少しずつ少しずつ滅びの道へ向かうのです。
土方歳三ゆかりの場所
今回の記事で出てきたゆかりの場所はこちらです。