清浄華院(しょうじょうけいん)は、京都御所の東、梨木神社のお向かいで蘆山寺のお隣にある浄土宗のお寺です。
「浄土に咲く蓮の華のように、清らかな修業ができる場所」という願いが込められた清浄華院。
今回は、慈悲深い『泣不動』でも有名な清浄華院を紹介します。
清浄華院の御本尊と由緒
清浄華院は、浄土宗八総大本山の中の1つで、知恩院・知恩寺・金戒光明寺と並び京都四本山の1つでもあります。
御本尊
清浄華院の御本尊は、大殿(御影堂)にお祀りされている法然上人御影ですが、大方丈には、阿弥陀堂の元本尊で平安後期に作られたと伝わる阿弥陀三尊像(阿弥陀如来・観世音菩薩・勢至菩薩)も安置されています。
由緒
清浄華院の創建は平安時代前期の貞観2年(860年)と伝わっています。
清和天皇の勅願により、天台宗の慈覚大師円仁が禁裏内道場(宮中に開いた道場)として建立されました。
当時は、”円・密・浄・戒”の四宗兼学の道場として、皇室とのつながりが深い鎮護国家の道場という位置づけでした。
承安5年(1175年)、浄土宗開祖の法然上人が、長年の厳しい修行の地であった比叡山を下り、東山吉水に草庵を結び、専修念仏を説きました。
法然上人の教えは、身分を問わず広まり、後白河法皇も法然上人に教えを請い、受戒を受けるほどでした。
高倉天皇や後鳥羽天皇も法然上人の教えを受け、受戒も受けました。
戒律…在家(出家していない人)の場合は、基本的には五戒(不殺生戒・不偸盗戒・不邪婬戒・不妄語戒・不飲酒戒)を言う
この後後白河法皇は、清浄華院を法然上人に賜り、これにより清浄華院は、浄土宗の寺院となりました。
このような由緒から、清浄華院の創立開山は慈覚大師、改宗開山を法然上人としています。
法然上人入滅後も、皇室とのつながりは続き、境内には多くの皇室の方々の陵墓があります。
平安以降の清浄華院
清浄華院の第五世・向阿(こうあ)上人の時代になり、清浄華院は三条坊門高倉(現在の御池通高倉東北角)に移転します。
当時の清浄華院は、多くの皇族や公家の帰依を受け、活発に活動していました。
南北朝時代の建武3年(1336)には、土御門室町(現在の室町通上長者)に移転。
ここは土御門内裏に近接し、花の御所(足利義満によって営まれた邸宅であり政治と文化の中心地)にも近い場所でした。
そのため、皇室・公家の帰依はさらに深まり、将軍家・武家からの信仰も受けるようになり、室町時代は清浄華院栄華の時代となりました。
応仁の乱と戦国時代
応仁元年(1467)に勃発し、以後10年の長きにわたり続いた戦により、京の町は焼け野原となります。
清浄華院も度々戦場となったため伽藍は灰燼に帰し、その勢力も大きく衰退しました。
しかし皇族・公家の帰依は変わらず、その親密な関係は続きます。
近世以降の清浄華院
清浄華院が現在の地に落ち着いたのは、豊臣秀吉の京の大改造に伴う移転でした。
江戸時代になっても皇室・公家の帰依は続き、歴代天皇の皇子・皇女の菩提寺となります。
一方で泣不動尊(なきふどうそん:後述)信仰により一般民衆からも広く信仰されるようになります。
境内には不動堂も建立され、信仰する人々により不動講も結成されました。
現在の清浄華院は決して広い境内ではありませんが、創建以来京の都にあり続け、皇室・公家だけでなく京の町衆にも寄り添い続けた寺院です。
これからも京都御所の東で、京の人々を見守りながら、平安と安寧を祈念し続けてくださることだと思います。
境内の見どころ
清浄華院の総門は、京都御所のすぐ東を南北に通る寺町通りに面しています。
総門をくぐると右手の方に大きなお堂が見えます。
大殿(御影堂)
清浄華院の本堂で、境内で一番大きなお堂です。
堂内の内陣中央には法然上人像が、内陣に向かって右側にはお寺にゆかりのある天皇や皇族の方々のお位牌が安置されています。

皇室ゆかりの寺院として、建物の各省には菊花紋があしらわれていますので、探してみてください
内陣の左側にお祀りされているのは、「泣不動尊」です。
「泣不動」とは、清浄華院の寺宝でもある『泣不動縁起絵巻』(重要文化財)の中で、弟子の師匠を思う心に感動して涙を流したという不動尊で、もともとは秘仏でしたが、今では常時見ることができます。
泣不動
三井寺の智興が死病にかかったとき、弟子の証空が身代わりになり、苦しんでいたところ、不動明王が証空の気持ちに感動し、哀れんで涙を流し、身代わりになったという説話。不動明王は証空の代わりに冥府へ行きますが、閻魔大王に礼拝され、不動明王は解放されます。
絵巻の中で、智興の病を証空に移し智興を助けたのは安倍晴明で、彼の陰陽師としての活躍を描いた絵巻としても知られています。
今日は平安時代の陰陽師【安倍 晴明】公のお命日。
清浄華院伝来の「泣不動尊」の由緒を伝える『泣不動縁起絵巻』に登場。この説話は当初晴明の験力を語るもので、後に不動尊が結びついた。両者は無関係だったが、近世には安倍晴明の祀った不動尊ということに。
寛弘2(1005)年9月26日寂。
南無阿弥陀仏 pic.twitter.com/2uCSgrHG4s— 大本山清浄華院 (@sho_jo_ke_in) September 26, 2022
また、大殿の前には、法然上人の御遺骨が納められた御骨塔があります。
不動堂と地蔵堂
総門の両脇には、不動堂と地蔵堂があります。
不動堂には、『泣不動縁起絵巻』ゆかりの半丈六不動明王座像、脇壇に石薬師尊と安倍晴明像がお祀りされています。
安倍晴明像は、『泣不動縁起』に登場する修法をしているそのままの姿をされています。
本日は毎月28日御縁日の泣不動法要でした〜
太鼓でお経を上げる賑やかなお勤めです。毎月28日15時から。 pic.twitter.com/4vuY3bCVl9— 大本山清浄華院 (@sho_jo_ke_in) August 28, 2025
地蔵堂には、子授け・安産・子育てのご利益があると言われる染殿地蔵がお祀りされています。
伝承によりますと、幕末の孝明天皇の典侍・中山慶子様が、染殿地蔵にお通いになり、そのご利益で明治天皇を授かったそうです。
会津藩主も逗留した阿弥陀堂(旧松林院)
総門を入って右手の方にあるのが、阿弥陀堂です。
ご本尊の阿弥陀如来坐像がお祀りされています。
この阿弥陀堂は、もともとは松林院という清浄華院の塔頭で、幕末には京都守護職会津藩の松平容保が半年ほど逗留していました。
容保公が逗留されている間に、新選組の近藤勇らが呼び出されたこともあるということです。
御所に近いという立地のために、その後も会津藩士がこちらで寄宿することがあったそうで、大河ドラマ「八重の桜」の主人公新島八重の兄、山本覚馬(西島秀俊さんが演じていました)などもいたそうですよ。
現在の阿弥陀堂は佛教大学の浄山学寮(宗門後継者養成道場)の教室としても使用されているため、授業中は拝観できない場合があります。
大方丈と小方丈
大殿の向かい、総門から入って右奥には、阿弥陀三尊像が安置されている大方丈と小方丈があります。
大方丈の阿弥陀如来坐像は、恵心僧都源信の作と言われ、両脇侍の観音菩薩像と生死菩薩像は、珍しい「大和座り」をされています。
大和座り…正座から少し腰を浮かしている状態。これは、すぐに立ち上がって阿弥陀様のお手伝いをするための姿勢です
おはようございます。 pic.twitter.com/Y2tITQP5zP
— 大本山清浄華院 (@sho_jo_ke_in) September 8, 2025
小方丈には、通称「浄土の庭」と呼ばれる庭があります。
秋の紅葉
あまり知られていませんが、清浄華院は知る人ぞ知る紅葉の名所。

出展:京都紅葉photo
紅葉のシーズンでも、それほど混雑はしませんので、ゆっくりと紅葉を楽しみたい方にはおすすめですよ。
【風の駅京都紅葉速報】
毎日楽しみな清浄華院の紅葉。
ほんまに綺麗。
誰もいないなあ。
今日も独り占め(笑)https://t.co/Y2jVpRElWk #BASEec #kyoto #紅葉 #風の駅 pic.twitter.com/TjRRYJL2oQ— 風の駅@出町柳【本屋&旅カフェ&オパール毛糸】 (@kazenoeki) November 12, 2016
清浄華院の御朱印
清浄華院では弥陀三尊・法然上人・泣不動・安倍晴明の御朱印をいただくことができます。
その他月替わりの御朱印もあり、どれも大変美しくて選ぶのにとても悩みました。
清浄華院【月替わり特別朱印】
本年は龍樹作『十二礼』から。『十二礼』は阿弥陀仏さまを讃える七言四句十二頌からなる偈頌(詩)で、浄土宗においては「六時礼讃」に引用され、声明曲「五念門」などで唱えられています。
8月は、第八頌より「瞻仰尊顔」です。 pic.twitter.com/xCBk28xvx0
— 大本山清浄華院 (@sho_jo_ke_in) July 31, 2025
おすすめの行事・祭事
清浄華院の最大かつ最高格のご法要が毎年4月20日に行われる「 御忌大会(ぎょきだいえ)」です。
4月20日 御忌大会開白法要 20~23日 御忌大会
この仏事は法然上人の年忌法要で、大永4年(1524)に後柏原天皇が知恩院に詔勅を下さって以降、天皇御願の法要として「御忌(ぎょき)」と呼ばれているそうです。
20日に開白法要が行われるのを始まりとして、23日までご法話や法要、法然上人を讃える諷誦文(ふじゅもん)のお唱えなどが行われます。
令和7年4月20日~23日【法然上人 御忌大会】
当院における最大かつ最高格の法要「御忌大会(ぎょきだいえ)」が奉修されます。
宗祖法然上人の年忌法要として、その遺徳を讃えて御恩に報います。
各日も関係者の参詣で混み合いますが、一般の方も参列可能です。ぜひお参りください。 pic.twitter.com/zhAYMgcyc3— 大本山清浄華院 (@sho_jo_ke_in) April 18, 2025
8月16日 盆施餓鬼会・献灯回向
施餓鬼(せがきえ)とは、飢えや渇きに苦しむ餓鬼(餓鬼道に落ちた霊魂や無縁仏)に飲食物をお供えして成仏を願うことで、特にお盆期間などに行われることが多い法要です。
清浄華院では、当日19時からは境内に灯籠が並べた献灯回向も行われ、20時に転嫁される五山の送り火と共に、幽玄で厳かな景色が広がります。
そして清浄華院さんの盂蘭盆会施餓鬼法要に。施餓鬼作法はやはり楽しい。数珠繰り📿もあったので盛り沢山。昨年は参拝出来なかったので今年は予定を空けたオッサンでした。大文字も綺麗に見れました。 pic.twitter.com/G1xKsr3NbF
— murphy (@murphy55183175) August 16, 2025
終わりに
清浄華院周辺には、御所や蘆山寺・梨木神社、少し南へ行くと下御霊神社や革堂などがあるほか素敵なカフェなども点在していて、散策にぴったりのエリアです。
北へ行けば下鴨神社もあり、季節の風情を楽しみながら寺社仏閣にもお参りできる、それでいてあまり混雑しない、私もお気に入りのコースです。
ゆったりと京歩きをしてみたい方はぜひ一度お散歩してみてください。
To preserve Kyoto’s beautiful cityscape, please observe proper etiquette.
- Please refrain from taking photos on the street.
- There are few trash cans in Kyoto, so please take your trash with you.
- Please refrain from loud conversations and noise.
- Please be quiet and observe proper photography etiquette at shrines and temples.
- Please do not touch or damage Buddhist statues or cultural properties.
京都の美しい街並みを残すため、マナーをお守りください
- 路上での写真撮影は控えめに
- 京都市内はゴミ箱が少ないのでゴミは持ち帰りましょう
- 大声での会話・騒音は控えましょう
- 神社仏閣では静かに行動し、撮影マナーを守りましょう
- 仏像や文化財を触ったり、傷つけたりしないでください
清浄華院の基本情報
- 開門時間 6:00~17:00
- 寺務所受付時間 9:00~17:00
- 境内自由





































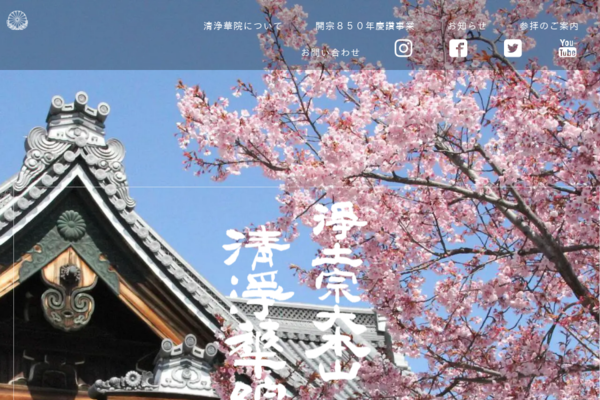


コメント